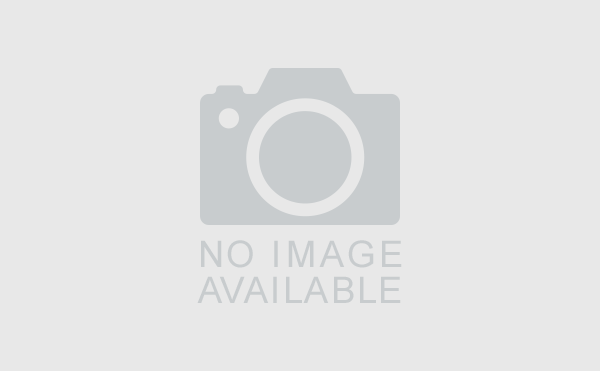6月議会 安心して保育できる環境を
中項目1:安心して保育できる環境について
保育環境とは安全で安心して成長・発達できる環境のことです。「人的環境」「物的環境」「自然・社会環境」の3つに分けられます。
人的環境は、保育士やその他の大人との関わりを通じて形成される環境です。子どもが安心感を持って信頼関係を築けるよう、保育士の関わり方や人間関係の調和が大切とされています。また、集団生活の中で他の子どもたちとの関係を学ぶことも、人的環境の1つです。
物的環境は、子どもが日常的に接する空間や道具、玩具などの物理的な環境のことです。安全性が確保された設備や適切な年齢に合った玩具・学習道具・遊び道具によって、子どもの好奇心や創造性を引き出します。さらに、室内外の空間配置や色彩・照明なども、子どもの発達に影響を与えるとされています。
自然・社会環境は、子どもが日常的に触れ合う自然や地域社会の環境です。季節の変化を感じられる自然環境や、地域の文化やイベントに参加する社会的な体験も自然・社会環境とされています。自然や地域との関わりを通じて、子どもの感受性や探求心、社会的スキルの発達を促します。
3つの環境の中でも人的環境が特に大切な環境の1つだと考えられます。
保育士の専門的な知識と温かい接し方は、子どもの情緒的発達や社会性の発達に大きな影響を与えるとされています。
子どもが安心して過ごせる環境とは心身ともに安定できて、安心感と信頼関係の中で自分らしく過ごせることです。目を見て話したり、子どもの話を最後まで聞き共感するなど子どもの気持ちに寄り添い、気持ちを受けとめることは、心の安定や信頼関係を気づくことができます。年齢や個別性に配慮した遊びができるよう考えたり発達に応じた保育をしていくことも必要です。
子どものやりたい気持ちや興味を持つ尊重し、保育者がゆったりとした気持ちで見守るためにはギリギリの人数の保育では難しいと考えます。怪我をしないか見守るだけで精一杯になってしまいます。
実際の働き方は長時間労働や保護者対応など精神的負担が大きい。
また配慮が必要なお子さんやアレルギーを持ったお子さんが増える中で益々負担が増えています。
仕事が大変で精神的な負担が大きにも関わらず、保育士の平均年収は、全産業平均よりも低水準で約100万円近く低いとされています。
保育施設は増加していますが保育士のなり手が増えていないので、保育士の確保が追いついていません。そのため仕事がきつくなりせっかく資格をとって保育士になっても若年層の離職率が高く、経験年数の積み重ねが困難になっており負のスパイラルが生まれています。
保育士が安心して働ける環境を整備していくことも必要です。
質問1. 安心して保育できる環境について市長の考えをお聞かせください。
中項目2:市で行っている施策について
質問2安心して保育できる環境整備のため大和市が行っている施策はどのようなことでしょうか
中項目3:保育士確保の課題と必要性
保育士の担い手不足は保育園からも声が上がっています。保育士の確保が進まないままだと子どもの安心して過ごす環境が担保されません。子どもの気持ちを尊重し、寄り添いながら保育するためには見守る保育士に余裕がなければなりません。
今後誰でも通園制度がはじまったら保育士の負担がもっともっと増えると不安声が上がっています。
大和市は政令都市や東京都町田市市や藤沢市が近隣にあるため、条件のいい他市へ働きに出てしまっている。保育の現場では他市の保育園に保育士が引き抜きもされるといったことも起きています。
保育士の担い手が減っているため保育士不足が叫ばれており、他市でも保育士の確保に他市も力を入れています。これは大和市でも喫緊の課題です。
【質問1】保育士不足が現場からも声が上がっているが保育士確保の課題についてどう捉えているか【質問2】保育士の確保の必要性を感じているか
答弁
保育所等では、利用児童数に応じて必要な数の保育士を確保することは施設運営の根幹であり、保育士確保は大きな課題であり、その必要性は高い。
市では、潜在保育士を対象とした公立保育園での就業体験、保育士確保に要する費用の市単独補助などを実施してきたが、保育士の確保においては、賃金水準の向上を図ることも重要であるため、近隣自治体と比べ低い水準にある施設型給付費の単価の区分を見直すよう、県を通じて国に要望してきた。
現在、国が隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との格差解消に向けた区分の見直しについて検討を行っており、今後の国の動向を注視していく。
中項目4: 保育士確保するために
今すぐにでもテコ入れして、保育士不足を解消しなければなりません。
そのためにも保育士の処遇改善していく必要があると考えます。
【質問1】他市では保育士確保のために単独で補助を行っている補助金がある
座間市や綾瀬市は月額10000円、海老名は質の向上を目指しこの4月から月額17000円補助金額が増えました。大和市においても他市と同様、保育士確保のための市の単独補助金を出していくべきではないでしょうか?
答弁
保育士の処遇については自治体による独自補助金ではなく、国の子ども・子育て支援制度のなかで取り組むべき施策と捉えており、保育士の増加や地域偏在の解消、全国統一の処遇改善策など、自治体間で格差を生まないための保育人材の確保に向けた取組を強化するよう、引き続き国に対する要望を行っていく。
【質問2】意欲を持って保育を学んできた保育士の奨学金の返済支援に取り組んでいる他市の事例があります。若い保育士を確保するために奨学金返済支援制度を実施することはできないでしょうか?
【質問3】保育士資格を取得したい人に補助を出すことは意欲を持って勉強し、資格取得後も大和市の保育所等で働いてもらうことにつながる。資格を取りたい人を応援する資格取得支援制度を実施できないでしょうか?
答弁
保育士の資格を得るための就学等に係る費用について、独自の支援を行う近隣の自治体があることは承知しているが、就学等の支援については、神奈川県が県社会福祉協議会を通じて実施している就学資金の支援制度を活用いただきたい。
【質問4】住宅手当を手厚くすることは一人暮らしの保育士を助けることができます。
若い保育士を確保するためや長く勤続ししてもらうためにも必要と考えるが住宅手当の補助の拡充をしてはいかがでしょうか?
答弁
保育士が居住するための住宅への支援は、国の補助制度を活用し、保育所等を通じて実施する宿舎借上げ支援事業により支援を行ってきた。神奈川県が今年度から、国の補助期間を超えて支援を行う方針が示されており、動向を注視していく。
【質問5】保育士を紹介してもらう人財派遣の紹介料に100万くらいかかり園の負担になっています。人財派遣の紹介料に対する補助の拡充はできないでしょうか?
答弁
本市では、民間保育所等における保育士確保支援のため、人材派遣会社への紹介手数料や有料募集広告に係る経費、保育士への就労奨励金などに対する補助を実施し、令和5年度には補助金を増額して支援の充実を図っている。
直近の1園当たりの平均補助額は約40万円であり、現在の補助上限額は適正であると考えている。
中項目5: 保育所等の課題
保育の現場で様々な課題があがっています。課題を解決していく必要があると考えます。そこで質問いたします。
【質問1】申し込みが多い保育所等にはどういう背景があるのか?
人気のあるところに申し込みをすることでもう一年育休を増やしたいといった背景はないのか?その対策はされているでしょうか?
答弁
保護者がどの保育所等を希望して申し込みをするかは、様々な要素を踏まえて、保護者が自ら選択しているものである。
保育所等の申し込みは、入所の希望を前提として受け付けており、保留を目的とした申し込みは受け付けていない。
育児休業期間中の方の申込みは、翌月1日までに元の職場へ復職することを条件としているほか、保育所等への内定を辞退した場合は、利用調整基準の指数をが減点している。申込内容の適正化を推進するために、毎月保育所等の空き状況を公開しているほか、保育コンシェルジュによる相談など利用者支援に努めており、今後も引き続き保護者のニーズに寄り添い、相談・情報提供に取り組んでいく。
【質問2】育児休暇が1年とれることが浸透してきているので0歳は自分で見ることができる。しかし1歳からでは保育所等に入れないと考えて0歳児から入れる人もいる。0歳児の受け入れを減らして1歳児の受け入れを増やすことができる様、園によって選ぶことでできれば1歳児の枠を増やすことができる。待機児童を出さないために保育所等を新たに作らなくても良くなる。
横浜市や町田市などで行っている様に0歳児の受け入れを減らして1歳児の枠を増やす補助金を導入して足りないとされている1歳枠を増やせる様にしてはどうでしょうか?
答弁
0歳児は通年で利用希望が多く、本市では0歳児についても1歳児と同様に高い保育ニーズがあるため、0歳児の受け入れを減らして1歳児の枠を増やす補助金の導入は難しいと考えている。
【質問3】アレルギー対応が園の負担になっています。相模原市が行っている事例がありますが、アレルギー対応に関する補助を行うことはできないでしょうか?
答弁
国において保育所におけるアレルギー対応のガイドラインが示されていることなどから、その対応方法は一般的になっているものと捉えており、現時点において補助制度新設は考えていない。
【質問4】園庭のない保育所等では児童の遊び場として公園を利用しているが他の保育所等と重なってしまうことがある。夏場などは水遊びができない、土を掘ることができないなど遊びが限定されている。園庭のない保育所等に通う児童が市保有地で遊ぶことはできないでしょうか?
保育所等を整備する際には、安心して遊ぶことが出来る場所として、原則として園庭の設置が必要だが、整備が困難な場合には、例外的に近隣の公園などを園庭の代替とすることが可能となっている。
園庭の無い保育所等には、園同士で交流をすることを目的として、公立保育園の園庭を利用していただけるよう、声がけを行っている。
【質問5】保育士のメンタルヘルス不調による退職が増えている。保育士が悩みを抱えている時に相談できる場があると離職しなくて済む可能性がある。保育士のメンタルヘルスに関する相談窓口を設置することはできないでしょうか?
答弁
本市独自の相談窓口は設置していないが、保育士を含む働く人のメンタルヘルスや健康についての相談窓口として、厚生労働省において「こころの耳相談」を設置しており、必要な際にはこちらをご案内していく。
中項目6: こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは、保護者の就労有無や理由を問わず、0〜2歳の未就園児が保育施設を時間単位で利用できる制度です。2023年6月に「こども未来戦略方針」のなかで打ち出され、2026年の本格始動を前に各地でモデル事業の実施や体制づくりが進められています。
これまで保育施設を利用するためには、保護者が働いているなど一定の条件を満たす必要がありました。しかし、こども誰でも通園制度は保護者が専業主婦(夫)であっても、理由を問わず利用できます。
こども誰でも通園制度のモデル事業を実施した地域の保育者による中間評価では、こども誰でも通園制度の負担が挙げられました。
ジョブメドレーが行った「預かりモデル事業になる仕事の負担の増加」のアンケートによると、普段の仕事の保育に加え預かる子どもの対応時間・労力の増加が60.8%、子どもが環境に慣れることが難しい、53.6%、事務仕事が増えた51.5%と続きます。
保育するこどもが増えることにより、対応時間・労力・業務量も増加し、それらが負担となっています。全国的に保育士が不足するなか、負担の増加は最大の懸念事項といえます。
通所児童であれば、十分な時間をかけてそれぞれのこどもの特性や家庭状況を把握できます。しかし、1ヶ月10時間という上限があるなか、短時間でそれらを把握し、安全な保育を提供しなければならない緊張感も伴います。
保護者にとっても、短時間・限られた回数のなかで希望どおりの日程で利用できるのか、育児の負担が軽くなるのか疑問が残ります。また、こどもが慣れるまでに時間がかかってしまい、家庭外で過ごす経験が充実したものにできるのかなどの不安もあるでしょう。
また、国は障がいの有無にかかわらず、こども誰でも通園制度を利用するための体制づくりを掲げていますが、現時点では明確な方針は示されていません。外出が難しい障がい児の利用が想定される居宅訪問型の事業形態は、新制度の対象に含まれておらず、検討段階です。
在園時の保育をしながら新制度を利用する子どもの安全を守りながら保育することは保育現場にとってかなりな負担になると考えられます。
保育士の人員の確保や環境を整備していく必要があると考えられます。
そこで質問です。
【質問1】具体的にどう進めていくのか
【質問2】保育所等への説明や今後のスケジュールについてはどうなっているのか
答弁
ども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこどもを対象とした、新たな通園給付であり令和8年度から、全国で開始される。
本市でも事業開始に向け、条例等の整備や実施施設の募集・認可など、具体的な実施方法について検討を進めている。
市内保育所等に7月までに実施施設の募集を案内し、調整を進めていく予定。
【質問3】課題をどう捉えているのか
答弁
本市では今後も保育所利用者数の増加が見込まれ、待機児童対策と並行して、本制度を実施する必要があり、実施施設の確保が大きな課題と捉えている。
【質問4】実施施設数の見込みについてはどのように考えているのか
答弁
令和8年度に向け、いくつかの施設から実施のご相談をいただいており、ニーズを見極めながら、今後、調整を進めていく。
【要望】
新学期が始まったばかりなのに保育士が辞めてしまった。保育士が足りないので今いる保育士で回すのが大変だが、募集してもなかなか来てもらえないと言った話しが
保育の現場から聞こえてきます。保育士の処遇改善は待ったなしの喫緊の課題です。年度途中であっても他市へ引き抜きされるといった状況も起こっています。本当はもう少し近くで働きたいと思っても、条件のいいところを選ぶということは当たり前だと思います。大和市の今の現状をしっかりと意識していただき保育士の処遇改善について動いていただけたらと思います。また保育の現場の様々な課題について解決していただくことを期待致します。
また今ある仕事の中でも保育士不足が叫ばれている中で誰でも通園制度が来年度から始まったらもっともっと大変なことになります。国は誰でも通園制度を2026年スタートさせると言っており、あと半年しかありません。今調整中とのことですが、現場はどのように進めるのか、どう対応していったらいいか分からず不安に思っています。
誰でも通園制度のモデル事業から課題が上がっているにも関わらず解決するまでに至っていないのに始めることだけは変わらないのは承知していますが、一刻も早く情報を集めて迅速な対応をお願い致します。