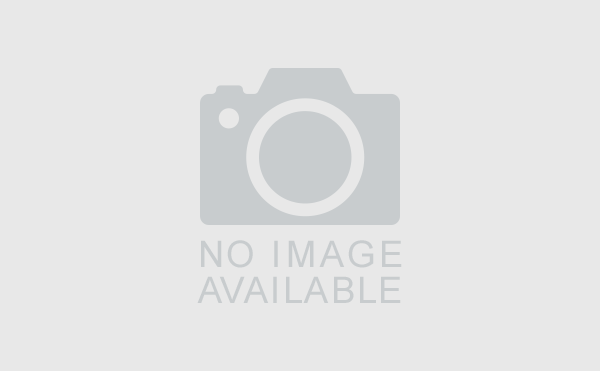6月議会 やさしいまちづくり〜安心して外出するためにまちにベンチを
中項目1:市民が安心して外出できる環境整備とベンチの必要性について
歩くことは生活習慣病の予防、便秘解消、骨を強くする効果があります。全身の筋バランスが整い、筋力アップをすることはもちろん、体力アップにも繋がります。またストレス解消になり気分を明るくする作用があります。一定のリズムで体の筋力を動かすとセロトニンが活性化し、気分が落ちつき、集中力が高まると言われています。不安や抗うつ感なども解消され元気でポジティブな気分になると言われています。海外で行われた研究では、認知症予防に効果的だと判明しています。様々な効果があり歩くことは人間の健康にとって大事なことです。
保健と福祉によると大和市の65歳以上の人口推移は、平成 27年は51926人でしたが、令和6年度は58495人と年々高齢者人口も増加し続けいます。高齢化はさらに進んでいくことが予測されます。
国土交通省が発表している高齢者の生活・外出特性についての中で、高齢者が無理なく休まずに歩ける距離が100mまでとする人が高齢者の1割、75歳以上は17%。また別調査では、自宅から駅やバス停までの許容距離として5分未満の数値を挙げる人が2割います。
外出するためには、高齢者や障がいのある方、妊婦さん、子供を連れた保護者が休憩する、場所の確保が必要です。体力に自信がなくても安心して外出ができるようにするには休む場所があちこちにあることです。また熱中症の対策や体調管理のためにもベンチでの休憩が命を守RUことにつながります。またベンチに座ることで会話や交流が生まれ、地域コミュニティの活性化にもつながります。
【質問】すべての市民が安心して外出できる環境を整えるのは市の大切な役割だと思いますが、環境整備とベンチの必要性について市長の考えをお聞かせください。
【市長答弁】
本市では、令和4年7月に「大和市総合交通施策」を改定し、その中で、子どもから高齢者まで、誰もが、気軽に外出することができ、無理なく移動できる「まちなか空間」の実現を目指し、道路のバリアフリー化や歩行空間の整備などを進めている。その具体的な取り組みの1つとして実施した、道路や公園等の公共空間へのベンチの設置については、買い物や散歩など、外出する方が途中で休憩したり、おしやべりするなど、市民の皆様が快適に過ごせる場所になったものと考えている。徒歩による移動は、高い運動効果が期待されるだけでなく、フレイル予防や健康増進、介護予防にも繋がるものと考えており、外出のきっかけとなるベンチの設置は、まちづくりの中において、必要な取り組みとして捉えている。
中項目2:ベンチの設置の現状について
今まで議会でも複数の議員から安心して外出できるためのベンチの設置の提案があったと思います。市としても施策を進め、可能なところからベンチの設置を進めていると思いますが
【質問】令和4年〜6年にかけて市が設置したベンチの数はどのくらいあるでしょうか
【答弁】
ベンチは、外出する方々の移動支援のみならず、人が集まる場所にもなると考え、現在取り組みを進めている大和駅周辺のまちづくりにおけるにぎわいの創出にもつなげるため、パイロットケースとして、令和4年度には、つきみ野や上和田など市内4箇所の遊歩道に、スツールといわれる一人掛けのベンチを12基設置した。
令和5年度には、桜森歩行者専用道である桜いこなーどや、鶴間駅から保健福祉センターまでの歩道など6箇所に10基、6年度は、大和駅の東側プロムナードや市役所東側の歩道など3箇所に4基、3年間で26基のベンチを設置した。
設置した結果、子育て世代や高齢者の方など、多くの方が利用していただいている状況から、ベンチの必要性をあらためて確認した。
中項目3:市民が主体のまちづくりについて
大和市では歩く健康づくり推進条例を制定されています。「歩く」ことは人間の基本的動作であり、適度な運動として、年齢、時間、場所を問わず、誰もが気軽に無理なく行うことができます。また、皆で楽しく取り組めば、周りの人へのあいさつからコミュニケーションが生まれ、まちに笑顔が広がります。このように「歩く」ことで心身の健康につながることが期待できます。わたしたちは 「歩く」 ことを通じて日常生活に根付いた身近な健康づくりに取り組み、一人ひとりの「歩く健康づくり」が実現するよう、この条例を制定します。
第7条 市は、基本理念に基づき、市民及び団体等と連携し、次に掲げる施策を実施する。
(1) 歩く健康づくりに関する情報の収集及び広報
(2) 歩く健康づくりに関するイベントの開催
(3) 歩く健康づくりに取り組みやすい環境整備
(4) その他歩く健康づくりに必要と認める施策
(市民及び団体等に対する支援)
第8条 市は、市民が歩く健康づくりに積極的に取り組むことができるよう、市民による活動又は団体等が行う事業に対し必要な支援を行うものとする。
(財政上の措置)
第9条 市は、歩く健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。としています。
大和市総合交通施策の5章の中で
基本目標2誰もが安心して外出できるまちなかの実現
『高齢者が人口が増加する中「自宅から駅まで歩いて出かけるとき、まちなかに座って休める場所が欲しい」と行った高齢者の声があります。』という記述があります。
展開施策4歩きたくなる街中空間の創出として
おでかけしたくなる街路空間の整備
⚫️子供から高齢者まで誰もが気軽におでかけできて移動できるまちなか空間を目指します。
⚫️道路や公園等の公共空間についてベンチの設置など休憩したり、おしゃべりしながら快適に過ごせる場所を創出して行きます
⚫️また沿道の企業や店舗、住宅などの協力を得ながら歩行者のための小さな休憩場所づくりを進めていくため、地域とともに取り組んでいく仕組み作りについて検討を進めます。
このように大和市の歩く健康づくり推進条例の中で市民が歩く健康づくりに積極的に取り組むことができるよう、市民による活動又は団体等が行う事業に対し必要な支援を行うものとすると言っています。また大和市総合交通施策の中でも休憩場所づくりを進めていくため、地域とともに取り組んでいく仕組み作りについて検討を進めますと言っています。
小項目1:地域に対する支援について
【質問】市民が主体的となってまちづくりを進めるにあたり、市はどのような支援を行うことができるか
【答弁】市民の皆様が集まり、地域が主体となってまちづくりを進めることは、市としても重要であると捉えている。その中で「ベンチの設置を進めたい」といった地域の課題解決につながるまちづくりの機運が高まった場合、「大和市みんなの街づくり条例」に基づく、「地区街づくり準備会」として、市に登録することで、活動経費の一部補助や、街づくり専門家の派遣等の支援を受けることが可能となる。「地区街づくり準備会」による、勉強会やワークショップを通じ、地区のまちづくり活動に対し賛同する方が増えることで、その地区におけるルールづくりに向けた取り組みも進み、また、ベンチの設置をきっかけとして、市民の皆様が主体となる、やさしいまちづくりの実現が、期待できると考えている。
小項目2:商店街に対する支援
【質問】商店街でベンチを設置したいという声がある場合、商店街に対し、市はどのような支援を行うことができるか
【答弁】
今年の4月からスタートした大和市商業戦略計画において、方向性の一つとして「滞在したい空間づくり」を掲げており、遊休地を活用した、ベンチや水飲み場など、商店街での滞在が心地良いものとなるための施設整備への支援を位置付けている。商店会等がそのような施設整備を実施する際、条件に合えば、制作や設置にかかる費用に対し、市から補助金を交付する制度が既にある。当該制度について、商店会等に対して引き続き周知を図っていくとともに、施設整備にとどまらない商店会としての主体的な諸活動に対しては、今後も積極的な支援を続けていく。
【意見】高齢者が外出すると少し歩いて疲れてしまいます。私の母も90を過ぎているのでちょっと歩いては疲れたと立ち止まります。でもそこにちょっと腰掛けて休むことができればまた復活して歩くことができて外出できる幅が広がります。
市で設置しているベンチは1基80万くらいかかると聞いています。市が設置しているベンチは高額なため予算がない中でなかなか設置が進みません。高齢者が無理なく歩ける距離が100メートルとすると、市の予算がいくらあっても足りません。そんな大層なものでなくてもちょっと腰を掛けられればいいのです。お金をかけなくてもちょっとした塀や花壇の枠でもいいのです。横浜市の日本大通りには花壇柵が座れるようになっています。資料3をご覧ください。その他にも様々なまちで腰をかけるところの工夫を凝らして実施しています。
また気軽に休めるところを増やしていくには、市民の協力と善意が必要です。
市民の善意で広がるまちづくりをしているまちをご紹介します。
吉祥寺の「赤いプロジェクト」は「まち」と椅子に宿る「ひと」の思い出を繋ぐものです。
椅子にはそれぞれ集めた際に伺った、元の持ち主の物語は貼られております。
この物語と設置場所は【赤い椅子プロジェクト】のHPでいつでも読むことができます。
店頭に置いて腰掛けてもらったり、レジカウンターの前に設置して荷物置きに使ってもらったり、腰掛けてもらったり、商品を陳列もできる。腰掛けていったおばあちゃんと会話が生まれ、お会計の時には椅子を荷物置きにしています。
ワークショップで赤く塗った椅子が現在どこに置かれてどのように使われているか、気になって置いてある椅子に座りにいったり、自分が提供した椅子や塗った椅子が使われていることの喜びや思い出ができて街が好きになってまた訪れたくなるような広がりが生まれています。街に置かれた赤い椅子は、子供や街を訪れる人たちの憩いの場となり「まち」と「ひと」をつないでいます。
資料4をご覧ください。大和駅の新橋通り商店街でもベンチを置いているお店があります。
お店の前にベンチを置いているお店の方に話しを伺うと、まちを歩く時のポイントにされている方が多く、お店の前でしばらく休んでいく人が多くいらしゃるそうです。新橋通り商店街のベンチや自前のベンチを置いているお店もありやさしいまちづくりが行われています。
このような活動が広がるよう、今後商店街の方々と一緒にベンチを増やす取り組みができたらいいなと思います。
また街角をよく観察してみると自分の敷地内に椅子を置いている方や切り株を置いているところがあります。
うちの敷地でよかったらひと休みして行ってもらえるかも、、、「まち」と「ひと」をつなぐことができたらやさしいまちづくりが広がっていきます。そんな人たちがどんどん増えていったらいいと思います。
ここに置いてあるけど座ってもいいのかな?と遠慮して座ることを躊躇してしまう方もいると思います。お座りくださいのプレートを下げたり、どうぞお座りくださいのステッカーを貼ることができたら心置きなく座れるようになると考えます。これはお金をかけずにできることなので是非取り組んでほしいと思います。
まちづくりの課題には市民が地域と一緒に主体となって考えていくことが大切です。市民が自ら動きどんなまちにしていきたいか、地域のどこにベンチが必要か考えていく市民が増えていくことが大切です。
歩けることが高齢者の幸福感に繋がるという研究事例も多くあるようです。多世代でウェルビーイングが実感できるまちづくりができるように市民の声を聞きながら、市民が参加しやすい仕組みづくりをともに考えていくことで市民参画が広がります。市民と地域と行政が一緒にまちづくりができればやさしいまちづくりができるはずです。今後に期待します。