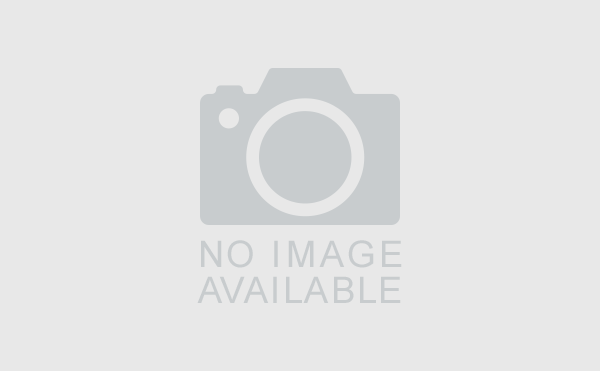9月議会一般質問 市民の外出の足の確保について
移動や外出にはいろいろな手段・方法があり、外出手段の確保は、日常生活の維持、地域の活性化、外出増加による高齢者のフレイル予防・介護予防など、多面的で公共的な意義があります。今回は、マイカーでの移動手段を確保することが難しい方々について取り上げます。
中項目1:福祉有償運送について
平成18年(2006年)に自家用有償旅客運送の一環として制度創設された「福祉有償運送」は、障害児・者や高齢者等の通院や買物などの足として欠かせない存在です。利用対象者は、身体障害者、精神障害者、知的障害者、要介護認定者、要支援認定者、基本チェックリスト該当者、その他の障害を有する者のうち、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者と規定されています。
本市においては、NPO法人であるワーカーズ・コレクティブケアびーくる、大和市腎友会、たんぽぽ、あゆみの4団体が登録を受けて運送を実施しており、ケアびーくる、腎友会、たんぽぽは市と協働関係にあります。この3団体のうち腎友会は9月末で有償運送から撤退することが決まっています。あゆみは知的障害児のみの送迎と聞いています。
福祉有償運送は、担い手不足、財源不足で、全国的に危機的な状況が続いています。制度が創設された直後の平成18年の登録団体数は2,430団体でした。その後平成31年の2,591団体をピークに減少を始め、本年3月末の国土交通省の集計では、2,244団体まで減りました。全国的に厳しい状況にあります。本市も例外ではありません。市は、協働事業関係にある団体に対し、福祉車両の駐車場等を無償で提供するなどの支援を行っていますが、団体の運転者不足による危機的状況が続いています。
一方、障害者や要介護認定者などの利用対象者は増える一方です。協働事業の一翼を担うケアびーくるには利用希望者が殺到しており、ここ2~3年は月平均10人(年間140人)の新規利用入会があると聞いています。昨年度の利用者実数は410人。利用の延べ人数(件数)は4,559人でした。しかし運転者不足のため依頼を完全には受けることができない状況にあります。市との協働事業で実施している、「福祉車両利用助成制度」の対象者から利用したいと申し込みがあっても日時によっては予約がいっぱいで受けられないことが発生しています。
ケアびーくるは、このままでは数年後の福祉有償運送は成り立たない、ドライバーが定年で引退してしまいこのまま担い手が見つからないと、後2年しか持ちこたえられそうにないと言っています。そうなると最も困るのは、単独では公共交通機関を使って外出できない障害者や高齢者です。制度があっても、福祉車両利用券をもらっても利用できなくては意味がありません。実質、事業者が一つしか稼働していないことも大きな問題です。
福祉有償運送については、よく知られていないかもしれませんが、対象者を運送しているだけではなく、引きこもりの人を連れ出し介護保険制度や障害者支援制度等につなぐ医師の診察に付添うなど困難ケースも多々あり、また、抗がん剤投与のための苦痛を伴う通院など、重病などと闘う利用者に寄添い・励ましながら安全運転に努めています。
福祉有償運送をめぐる社会情勢は、制度創設時から大きく変化しています。運転者についても、共働き、定年退職後の再雇用他仕事を続けることが主となる世の中で、ボランティア性の高い事業、最低賃金ぎりぎり程度の報酬では運転者がなかなか見つからない現状があります。その他、社会保険の加入なども考えると、事業者が運転者を増やすために個々にできる努力にも限界があります。
【質問1】市は福祉有償運送の価値や重要性をどのように認識しておられますか。また現在の危機的状況の対処方法について市長の考えをお聞かせください。
【市長答弁】福祉有償運送は、特定非営利活動法人や社会福祉法人等の非営利法人が、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方や、身体に障がいのある方など、単独で公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に会員登録を行い、通院、通所、余暇などの外出支援を有償で行う自家用自動車による移送サービスである。
本市は、平成15年、国からみんなで進める地域福祉特区の認定を受け、全国に先駆けて福祉有償運送を開始し、地域住民の外出の足を確保するために必要な福祉有償運送に関する協議会を開催するなど、福祉有償運送事業者を支援するとともに、移動に制約を受ける方の外出支援に取り組んできた。高齢者世帯の増加等により、移動に制約を受ける方の人数は年々増加傾向にあり、外出機会の確保とフレイル予防などの観点からも福祉有償運送の重要性は今後ますます高まるものと認識している。
一方、定年退職後も働く人や共働き世帯が増加している中、福祉有償運送は、運転手の高齢化が進んでおり、更にボランティア的要素が濃く、報酬が低いことなどから、その担い手不足が深刻化している状況にあり、今後移動制約者の輸送希望に十分応えることができないことも想定される。
このような状況を踏まえ、福祉有償運送を維持するためには、新たな運転者を確保することが、とりわけ重要であると考え、和6年度から、福祉有償運送の運転業務を担う際に必要となる国土交通大臣認定講習を市が主催し、参加者が費用を負担することなく受講できる環境を整え、受講者43名、そのうち6名が市内事業者にドライバー登録をされた。
本市としては、厳しい財政状況にあるが、福祉有償運送制度の啓発や講習会への参加について積極的に周知活動を行うとともに、今後も担い手確保につながる運転者講習会を継続して開催することで、市民の外出の大切な足である輸送手段としてその人材確保に努めていく。
【質問2】協働事業の事業者を増やすことについて市の考えをお聞かせください。
【答弁】市では、市民等、事業者及び市が、お互いの提案に基づいて協力して実施する社会に貢献する事業を協働事業として位置づけ、令和7年8月末時点で11の協働事業が実施をされています。
協働事業の事業者を増やしていくことは、さまざまな地域課題の解決に向けて大変重要なことであり、新たな協働事業が創出されるとともに、事業を担う市民活動団体の活動が活発になることは喫緊の課題であると認識しています。
新たな協働事業の創出や協働事業者を増やしていくためには、ボランティアの発掘、育成をはじめ、市民活動団体に対する財政的支援に加えて、相談体制の充実等が必要であることからも、市民活動センターとの連携を図りながら、活動しやすい環境づくりに努めています。
なお、外出支援を行なう協働事業者からの相談を受け、やまとボランティア総合案内所での紹介をしたところ、新たな運転会員の入会につながった事例等もありますので、今後も引き続き、協働事業者への支援を積極的に行っていきます。
中項目2:福祉有償運送運転者講習会について
本市は、運転者不足に対応するため、県内他市の事例を踏まえて、昨年度から、大臣認定運転者講習を運転者講習実施機関に委託して年2回主催・開催しています。昨年度の運転者講習の受講者は、8月は17人、11月は27人でした。2回目の講習会は定員を超える応募、受講があったものの、運転者増に結びついていません。
今年度は11月に2回開催されます。市が主催することについては、「広報やまと」や市のホームページ等で広く広報できる強みがあります。しかし残念ながら、運転者講習の広報は目立っていません。紙面の扱いは小さく、ホームページは、講習会があることを知っている人しかたどり着けない状況です。
そこで質問致します。
【質問3】昨年度の受講者44人のうち、福祉有償運送の運転者になったのは何人でしょうか。昨年度は「社協だより」に講習会のお知らせが掲載されて以降、申し込みが増えた経過がありますが、すでに「社協だより」は発行されていません。今年度はどのような工夫で受講者や運転者を発掘しようとしているかお聞かせください。
運転講習会の日程をホームページで掲載しているがわかりにくいと市民からの声があがっています。参加者募集の間だけでもトップページにバナーで掲載するなど、ホームページを開いた人が興味を持つような掲載の仕方を工夫できないでしょうか。
子どもが幼稚園や学校に行っている間に働きたいと思っている女性に向けて、ラインやSNSを使って広報したり、中間層、高齢者にはチラシを置く場所についての工夫をするなど、ターゲットに向けて効果的な広報をしてほしいとの要望がでていますが、いかがでしょうか。
問題は、運転者講習だけ広報しても市民には伝わらないと言うことです。運転者講習だけでなく、福祉有償運送の存在と役割・必要性の広報が重要です。市は、ファミリーサポートセンター事業については、事業の概要や目的、仕組等を毎年10月または11月に広報やまとで特集を組んで紹介し、利用者と支援者の双方が理解しやすい仕組みをつくっています。ファミリーサポートセンター事業のように、「広報やまと」での特集と運転者講習をリンクして担い手を増やしてはどうでしょうか。講習修了者の福祉有償運送運転者就任の状況についてと講習会の周知・広報について市の考えをお聞かせください
【部長答弁】
福祉有償運送運転者講習会については、令和6年度に2回開催し、1回目16名、2回目は定員を超える27名、計43名の方に受講いただき、そのうち、市内福祉有償運送事業者の運転者として登録された方は6名となっている。
今年度も11月に2回開催する予定にしており、講習会の周知、広報については、市のホームページや広報やまとへの掲載に加え、民生委員・児童委員や地区社会福祉協議会等、様々な団体の皆様に関心が広がるよう丁寧に周知を進めていく。
今後、より幅広い世代の多くの方に関心をお持ちいただくため、新たに、大和市及び大和市社会福祉協議会やまとボランティアセンターの公式LINEアカウントからの案内やぷらっと高座渋谷、子育て支援施設等へ講習案内を配架するなど、幅広い年齢層の方に参加していただけるよう取り組みを進めていく。
なお、市ホームページについては、視認性を高めるとともに、講習会の周知に留まらず、福祉有償運送の有益性をご理解いただけるよう内容の充実を図るほか、市ホームページにアクセスできる二次元コードを広報やまとに掲載するなど、周知の手段や方法の工夫に努めていく。
中項目3:訪問型サービス・活動D の実施について答弁
本市の「おひとりさま支援条例」の前文は次のように書かれています。「ひとりぼっちで頼れる人がなく、人間関係を喪失することで段々と社会との関係が希薄になり、出かけることや、人とのコミュニケーションの機会が減少していくことも少なくありません。 しかし、人間にとって、外出や他者との関わりはとても重要です。それぞれが無理のない範囲で外出し、人や社会とのつながりを持ち続けることによって、日々の暮らしがより彩り豊かなものとなり、このことは心身の健康にも関係してきます」と。つまり、外出を促進することで交流の機会が増え心の健康につながるとの市の認識があります。
しかし、おひとりさま高齢者を対象とした令和5年度のアンケート調査のなかの「あなたと同居していない家族や友人たちとのコミュニケーション頻度」を問う質問に対し、直接会って話すことが全くないと回答しているおひとりさまは22%もあり、月1回未満の18%を合せると、本市の独居高齢者の実に40%が他者との交流に課題を抱えています。
先ほどは福祉有償運送について質問しましたが、福祉有償運送の対象者ではない一般の高齢者についても、通院や買物を含め困りごとが多々ある高齢者世帯や独居世帯が全国的に増えており、この課題を受けて、互助型の外出支援活動が全国に広がっています。静岡県域では、100か所近く、神奈川県内でも50を超える地域で互助型の移動支援が行われています。
国土交通省は、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」を昨年3月に改正施行したところです。前文では、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送についても、公共交通機関や自家用有償旅客運送の果たす役割を補完することが重要である」と記されています。
本市においては、中央地区では支え合い協議体による話し合いの結果、社会福祉法人徳寿会晃風園の支援を受けて、買物支援や生活支援サービスなどとの一体運送をが行われています。
厚生労働省老健局は昨年8月に総合事業に関する改定を行い、サービス・活動Bにおいて、市町村が要支援や基本チェックリスト該当者「以外」の者を対象にすることも参加者に対する活動を事業の目的を達成するための随時的な活動と判断する場合は、定額で補助できる仕組みとなりました。
八王子市では地域主体による助け合い・社会参加応援事業を行っています。高齢者の日常生活における様々な困りごとを支援する「生活支援」や、高齢者の社会参加と交流を促進する「通いの場」を運営する地域主体の団体を「八王子市地域助け合い・社会参加応援団体」として登録しています。応募の要件としては要支援を受けている方を含む65歳以上の高齢者に対し、訪問による生活支援サービスを提供する団体で、サービス提供を行う住民が5名以上いること。地域住民の自主活動であること(有償または無償ボランティア)。助成金は月額上限3万です。サービス提供を行う住民が5人から始められることからハードルが低いので登録団体がどんどん増えていています。現在45団体あり、そのうち車を利用した外出付き添いは24団体です。半分以上の団体が車を利用した外出付き添いを行っていて、その他にも買い物付き添いや通院や散歩などの外出支援を行っている団体があります。いかに高齢者の方々が外出することに対して不安を持ち、日常の困りごととして支援して欲しいというニーズが多いのかということがわかります。また生活支援コーディネーターを置いていて、地域のニーズを把握するとともに、必要とされる生活支援サービスを提供するためのしくみづくりや地域で活躍する担い手の人材育成などを通じ、地域支援を進めています。
地域のために活動してみたい、ご近所同士で集まれる居場所を作りたい、生活支援を行う団体を立ち上げたい、地域が抱えている困りごとを解決したいといったときには生活支援コーティネーターに相談することができます。
本市においては高齢者がいる世帯の42.4%が独居高齢者という(国の平均32%を大幅に上回る状況の中で)生活支援サービスの充実とあわせて住民互助による移動支援を促進すべきではないでしょうか?中央地区だけでなくその他の地域で増やすことができたら福祉有償運送の負担を減らすことができると考えます。
【質問4】 困りごとに対応するとしての外出支援について互助活動について、訪問型サービス・活動Dを実施する予定はあるでしょうか
【部長答弁】
介護予防・日常生活支援総合事業で実施する訪問型サービス・活動Dは、地域住民が主体となり、自身で外出することに困難を感じている高齢の方を対象に、通院や買い物などに伴う外出を支援するサービスである。
本市では、利用者が、原則、介護予防の必要性を判定する基本チェックリストの該当者等に限定されること、また、車両や地域における運転ボランティアの確保、事故発生時の対応や、車両の維持管理等の課題があることを考慮し、訪問型サービス・活動Dについては、実施していない。
介護予防・日常生活支援総合事業は、国の交付金に上限額が定められており、本市では、自立支援や、重症化を防止するため、機能訓練や、認知症予防等の介護予防事業も充実させており、交付金を十二分に活用している。
今後、事業の実施にあたっては、地域からの発意が必要不可欠と考えており、地域からの提案があった場合には、その実現性や継続性、総合事業の実施状況等を勘案し、実施について検討する。
中項目4:コミュニティバスについて
本市のコミュニティバスは、鉄道や路線バスなど公共交通の不便な地域を対象としてお年寄りや子育て世代などの移動に制約がある方々の日中の移動手段の確保するため運行しています。
2004年から小型バス車両を使用する「のろっと」(現在北部ルート、南部ルートの2路線)を運行し、2014年からワゴン車両を使用する「やまとんGO」(現在中央林間西側地域・相模大塚地域・深見地域・桜ヶ丘地区の4路線)を運行しています。
「のろっと」のうち南部ルートは以前から乗車率が高かったのですが、北部ルートについても座れない便が日常になるほど、高齢者を中心に利用が広がっています。
【質問5】「のろっと」南北ルートならびに「やまとんGO」の各路線について、利用者数や収支、委託料の推移についてお聞かせください。
【答弁】
コミュニティバス「のろっと」の利用者数については、和4年度は約35万3千人、5年度は約38万3千人、6年度は約41万人、「やまとんGO」は令和4年度は約30万4千人、5年度は約34万人、6年度は約35万8千人となっている。
運行委託費については、令和4年度は約4億1千万円、5年度は約4億5千万円、6年度は約4億7千万円、運賃収入については、和4年度は約7千8百万円、5年度は約8千4百万円、6年度は約9千万円となっている。
このように、利用者数も運賃収入も年々増加しておりますが、それを上回るペースで、燃料費や人件費等の運行委託費が高騰している状況にあり、このため、収支率は、過去3年を平均すると、「のろっと」は約33%、「やまとんGO」は約14%と、横ばいの状況が続いている。
【質問6】 やまとんGOは30分に1便の運行だが、のろっとは1時間半ごとの運行です。便数を増やしてほしいと言う要望は市にも届いていると思うが、どのように検討されているでしょうか。
【答弁】「のろっと」の増便につきまして、これまでも市民の方から度々ご意見をいただいておりますが、厳しい財政状況を踏まえた上で、民間路線バス等の状況も考慮し、運行ルートやダイヤを見直すなど、公共交通全体での最適化・効率化とあわせ検討を進めていく。
のろっとは、A系統とB系統がある。出発直後の便は遅延がないが、ルートの終わりのバス停では遅延が多々起きています。どのくらいの遅延か待っている人にわかれば他の方策を講じることができると思います。
【質問1】 バス遅延に関する情報について、市はどのように提供しているでしょうか。
【答弁】現在、大幅な遅延が発生した場合には、市のホームページやLINEで情報を発言し、直接電話での問い合わせにも対応しているほか、運行事業者に直接連絡していただくことでも、運行状況を確認することが可能となっている。
バスのロケーションシステムにつきましては、既に「のろっと」に導入し多くの方に利用していただいておりますが、「やまとんGO」につきましては、車両台数も多く、導入する際の初期費用や維持費用等、多額の費用が見込まれるため、今後、財政状況等を踏まえ、適正に判断していく。
【要望】
ご答弁ありがとうございます。高齢者世帯の増加等により移動に制約を受ける方の人数は年々増加傾向にあり 、外出機会 の確保とフレイル予防などの観点からも福祉有償運送の重要性は今後ますま高まるものと認 識してるとのことでした。
一般に公共交通機関を使えない方と言えば、即車いす使用の方とイメージされがちですが、福祉有償運送を利用する方の7割が障がい者手帳を持たず、介護認定も受けておられないがステップを使ったり少しサポートすればセダンに乗れる方だということです。自立した生活を送れる方にとって、外出の機会が減って要介護・要支援にならないためにも非常に重要な部分です。
高齢者は月7回の外出で元気でいられると言われています。元気でいれば家族にも迷惑をかけず子育て世代を助けることになります。またフレイル予防になります。今利用をしている方たちが支援を受けられなくなることは子世代に負担を強いてしまうことになりかねません。少しサポートすれば自立した生活を送れる方を要支援・要介護に進まないために、ここの層の方を支援するためにも福祉有償運送がなくなることがないよう対策していくとが必要です。
一方、定年退職後も働く人や共働き世帯が増加している中、福祉有償運送は、運転手の高齢化が進んでおり、更にボランティア的要素が濃く、報酬が低いことなどから、その担い手不足が深刻化している状況にあり、今後移動制約者の輸送希望に十分応えることができないことも想定されることも市でも認識しておられる。
運転者講習会の受講者43名、そのうち6名が市内事業者にドライバー登録をされましたが、現状残っているのは1名でなかなか結びついていないのが現状です。新たな協働事業の創出や協働事業者を増やしていくため、ボランティアの発掘、育成をはじめ、市民活動団体に対する財政的支援に加えて、相談体制の充実等が必要であることからも、市民活動センターとの連携を図りながら、活動しやすい環境づくりに努めているとのことですが、ボランティアの発掘もあまり増えてはいません。
現在役割がそれぞれ違う課でやっているため課題や問題がなかなか見えずらいという問題もあると思うのですが、縦割りではなく横のつながりで、連携して取り組んでいく必要があると考えます。福祉有償運送を衰退さないための組織と仕組みづくりを考えていただくことを要望致します。
運転者講習会の周知については、ホームページを何回も段階を踏まないとたどり着けなくて見にくいという意見があると述べされていただいたのですが、トップページからすぐ飛べるように早速対応していただいたこと、感謝いたします。幼稚園や学校に行っている間に働きたいと思っている方や、定年して少しゆっくりしよう、でも少し何か始めたいと思っている世代にアプローチするなど、ターゲットを絞りより効果的な方法を考えて周知していたけますようお願い致します。
今後ますます増えていくことが予想される高齢者が、マイカーでの移動が難しくなった時の移動手段をどう確保していくのか考えていくべき時が来ていると思います。ニーズはあるのに受け皿がないということがすでに起き始めています。市として危機感を持って高齢者の移動支援について考えていただけますよう要望いたします。