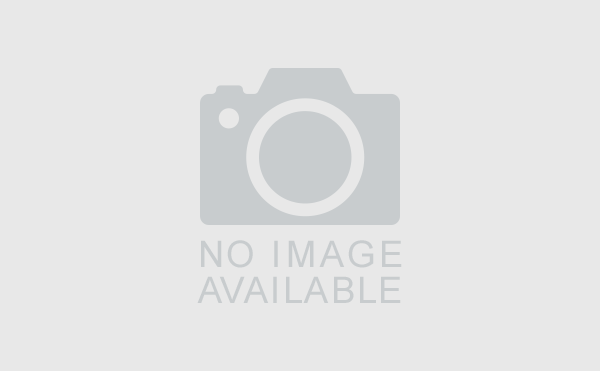9月議会一般質問 子どもの目の健康について
中項目1:乳幼児における目の健康について
生まれた直後は視力が0.01〜0.02程度で、光や大きな形に反応する段階ですが、生後3ヶ月ごろ焦点を合わせて人の顔を追えるようになります。生後6ヶ月頃に立体的に物を捉えられるようになり、1歳以降色のあるものをよく追えるようになり、視力も急速に発達し、6歳ごろ視力の発達がほぼ完成します。
弱視は遠視・乱視・強度近視など屈折異常、斜視、左右の視力の差が大きい、黒目の中心部分の濁り、眼瞼下垂などがありますが、ほとんどの原因は屈折異常によるものです。新生児の目は遠視ですが成長とともにピントが合うように視力を発達させる時期に強い屈折異常があることで、網膜に焦点が合わず、外界の視覚的な刺激を得られなくなります。これが原因で弱視が起こります。
早期発見により強い屈折異常(遠視、近視、乱視や斜視)などが見つかった場合、治療により、視力の回復が期待できますが、6歳以降になると回復が困難になります。小さい子どもの場合、自分の視力に問題があるか自覚することや大人にきちんと言葉で伝えることが難しい時期でもあります。
見る力が発達する乳幼児期に治療することが重要で、3歳児健診の視力検査は大きな節目になります。早期発見して治療により視力が回復できるように、1次検査で屈折検査機器を導入してはどうかと同じ会派の山崎元議員が提案したことによって大和市でも1次検査で屈折検査機器を導入して検査を行うことになりました。
そこで質問致します。
【質問1】大和市では乳幼児健康検査でどのように目の健康を確認しているでしょうか
【答弁】目の機能は3歳頃までに急速に発達し、6歳から8歳頃に完成するもので、目の疾患が見逃され、治療が遅れると、生涯十分な視力が得られないことがあるとされているため、早期に発見して治療につなげることが何よりも重要です。
4か月児、8か月児、1歳6か月児、3歳6か月児を対象に実施している乳幼児健康診査において、目の健康についても、事前のアンケートによる保護者からの情報や医師の診察所見により、必要に応じ精密検査の受診を案内しています。さらに、令和4年度からは、屈折検査機器を導入し、3歳6か月児健康診査にて活用することで、弱視や目の異常の早期発見に努めております。
【質問2】3歳6か月児健康診査の視覚検査での二次検査及び精密検査を受ける人数はどのくらいでしょうか
【答弁】令和6年度の3歳6か月児健康診査の受診者数1,810人のうち、視覚検査の二次検査対象数は625人、その結果、さらに医療機関での精密検査が必要とされた人数は156人でございました。
【質問3】精密検査後の診断結果としてどのような異常がみられているかお聞かせください
【答弁】精密検査後の診断結果について、把握できている最新のデータとなる令和5年度の結果によると、いずれも延べ人数で、近視や乱視などの屈折異常が110人、弱視が44人、斜視などの眼位や眼球運動の異常が22人でございました
【質問4】屈折検査機器導入前後の精密検査対象者割合の変化について教えてください
【答弁】3歳6か月児健康診査の受診者総数に対して精密検査対象となった子どもの割合は、屈折検査機器を導入した和4年度から6年度の平均で、9.3%となっております。これは導入前の3年間の平均5.6%の約1.7倍であり、早期発見に一定の効果があったものと考えております。
中項目2:小中学生における目の健康について
子どもの近視が増えていてここ数十年で政界的に急増しており、1990年代に約24%だった子どもの近視率は2023年には35.8%に上昇しています。
韓国のソウル国立大学校 医学部眼科学准教授のYoung Kook Kim氏らによるによると、2050年までに世界の人口の約半数が近視になると予測しています。近視患者の急激な増加の予測は、都市化が進んだ社会でよく見られる環境要因に後押しされている可能性が高く、その主な要因として挙げられるのは、近くを見る活動の増加と屋外での活動の減少だ」と指摘しています。Kim氏らは、45件の先行研究の33万5,524人(平均年齢9.3歳)のデータを統合して解析した結果、「近視リスクはスクリーンタイムが1時間を超えると4時間まで顕著に上昇し、4時間を超えると上昇の仕方が鈍化することが示された」と述べています。
日本でも深刻な傾向が確認されています。文部科学省の学校保健統計では、裸眼視力1.0未満の子ども(近視含む)小学学校は令和元年は34.57%でしたが令和6年は36.84%、中学生は令和元年が57.47%でしたが令和6年は60.61%、いずれも過去最高を更新しています。
厚生労働省が発表している「子どものスクリーンタイムの変化」の1回目調査は2020年4~5月実施、第3回目調査は2020年9~10月実施されています。d小学生1〜3年生の低学年は30分以上2時間未満が1回目の調査は29.2%でしたが3回目は51.3%に、2時間以上4時間未満は1回目が38.4%、3回目が32.9で、近視に影響がある1〜4時間を合わせると1回目が67.6%から84.2%と大きくスクリーンタイムが増えています。4〜6年の高学年は30分〜2時間未満は1回目25.0%でしたが3回目は41.2%、2時間以上4時間未満は1回目37.4%、3回目は36.0でしたが、近視に影響がある1〜4時間を合わせると62.4%が77.2%と大きくスクリーン時間が増えています。1回目と3回目は同じ年に2ヶ月間ずつ調査が行われたものですが、いずれもコロナ禍で家にいた期間ですが半年間でスクリーンタイムがとても増えたことがわかります。
そこで質問します
【質問1】裸眼視力1.0未満の小中学生の割合の推移について令和元年と令和6年の小中それぞれの数値を教えて下さい。
【答弁】裸眼視力 1.0未満の小中学生の割合は、小学生は、和元年度は35.8%、6年度は38.9%中学生は、和年度は51.9%、6年度は61.8%と、増加傾向です。
【質問2】小中学生の視力の低下をどのように捉えているか、児童生徒の目を守ることに対して市はどのような考えがあるでしょうか。見解をお聞かせください。
【答弁】小中学生の視力の低下については、近年の生活環境の変化によりスマートフォンやタブレットなどを使用する時間が増加し、目に負担がかかっていることが一因であると捉えており、小中学生の目の健康状態について十分留意する必要があると認識しています。
教育先進国と言われている北欧 スウェーデンでは、2010年にタブレットやPCを1人1台付与する計画を進め、紙の教科書を原則として廃止するなど、教育現場にITを取り入れてきました。当時デジタル社会にいち早く対応した取り組みとして、日本でも話題になりました。しかし、2023年8月の新学期からスウェーデン全土の学校で、キーボード操作の練習時間を減らし、「静かに本を読む・手書きの練習をする時間」に重点が置かれるようになりました。
実は近年、2016年から2021年にかけてスウェーデンの児童の読解力は低下しています。小学4年生の読解力に関する国際的な評価である「国際読解力調査(PIRLS)」において、ヨーロッパ平均は上回っているものの、毎年ポイントを下げています。
また子どもたちの集中力が続かない、考えが深まらない、長文の読み書きができないなどの弊害が出ているそうです。この理由として、関係構築能力や注意力、集中力、読み書きや計算能力などの基礎的なスキルは、アナログ活動によって最もよく習得できることが実証されています。特に低学年は物理的な本に重点を置くべきである、としています。政府は保育園へタブレットを導入するなど、国を挙げて教育の超デジタル化を推進してきましたが、従来の学習方法を取り戻し6歳以下の子供を対象とするデジタル学習は完全に撤廃し、2023年に学校向けの書籍購入費用として6億8500万クローネ(約148億円)相当の予算をつけました。さらに、学校に教科書を再配布するための予算として、2024年から2025年にかけて年間5億クローネ(約108億円)が投じられる予定です。
スウェーデンのカロリンスカ研究所も、「デジタル情報源から知識を得るのではなく、印刷された教科書と教師の専門知識を通じて知識を得ることに重点を戻すべきだと考えている」との声明を発表しています。そして「学習の記憶は、どのあたりに書かれていたかといった物理的な位置情報にも関連しており、画面上の情報は記憶に残りにくい」と指摘しています。デジタル化を進めてきたスウェーデン、フィンランドなど北欧では紙に戻す取り組みを始めています。
9月5日NHKニュースによるとタブレット端末に取り込んで使う「デジタル教科書」は2019年度から紙の教科書と併用する形であれば小中学校の使用が認められていて、2030年度には正式な教科書としての導入が検討されている。一方、専門家からは「小学校の低学年では、かえって理解度が低下した」とか「視力が悪くなるなど健康面も心配だ」などといった指摘もあがってます。このため文部科学省はデジタル教科書を学校現場に導入する際のガイドラインを策定する方針を固めたとのことです。今後「デジタル教科書」が導入されることになるとますます近視が増えることが予想できます。ガイドラインを策定するということなので今後は注視していく必要があります。
大和市では今現在タブレット端末をどのように使っているのかお聞きしたところ調べ学習などに使うため、長時間連続して使うことはないとのことです。
市内の小中学校で端末を活用して授業を行った1日の回数を教員にアンケートをとって端末使用状況を調査していますが、令和3年は0.9回、令和4年1.15回、令和5年1.33回、令和6年1.77回と年々増えています。タブレットを持ち帰る際は夜は使えないようにしていると聞いていますが、スマホは家庭で制限をかけないと見えれてしまうのでずっと見続けてしまうのではないかと懸念しています。
過去に携帯を子どもに与える時に子どもと話しあうためのツールとして「スマホ18の約束」が話題になりました。これはアメリカのあるお母さんが13歳の息子さんにスマホを与えてもいいか悩んだ末に作った息子さんとの間の契約書です。「私はあなたを健康で豊かな人間性を持った、現代テクノロジーをうまく活用していける大人に育てなければならない」とうことをお母さんから息子へ説明し、スマホを使う時の約束をするといった内容です。愛情がたくさんこもった内容で、家庭の中で知っているといい情報だと思います。家庭の中でスマホの使い方について話しあうきっかけになると思うので、学校の中で紹介していくことも予防になると思います。
学校や生活の中で目を休めることの重要性や端末を長時間使用することで近視になる人が増えている情報などを積極的に共有していくべきではないかと考えます。
そこで質問いたします。
【質問3】子どもの目の健康を守ための現状の取り組みや指導についてお聞かせください
【答弁】教育委員会では、裸眼視力1.0未満の児童生徒について、保護者に対して視力検査結果をお知らせし、医療機関への受診勧告を行っています。また、小中学校の全クラスに視力検査表を配付し、児童生徒が日常的に自ら視力を測定し、現状を把握できる環境を整えています。
各学校では、「ほけんだより」を通し、子どもの健康全般について周知する中で、特に「目の愛護デー」がある10月に、目のしくみなどを特集し啓発、予防に努めています。
【質問4】端末を使用することによる視力の低下が心配されるためルールを作るなど注意喚起をしていく必要があると思うがいかがでしょうか
【答弁】児童生徒に対し教育委員会で作成した「クロームブック活用の手引き」により発達段階に応じた注意喚起を行うと共に、保護者に対しても健康面に留意するよう求めています。
外で過ごす時間が短いほど近視率が高くなる傾向があることがわかっています。台湾では2010年から学校教育の中で毎日2時間の屋外活動を義務付けています。一度に2時間ではなく、休み時間の外遊びや運動を合わせて、合計2時間以上を屋外で過ごせるカリキュラムを組んでいます。この取り組みにより子どもの近視の進行率が10%以上低下したという報告があります。これは世界で初めての発見で大きく注目されています。
中国では子どもの近視対策として2021年から塾やゲームなどの規制を導入しましたが、これは台湾の大規模臨床試験結果に影響されたものです。WHO(世界保健機構)は1日2時間以上の屋外活動を推奨しています。2019年にはWHOも視力に関する初めてのレポートを作成した中で「最も頻度の高い眼疾患である近視と、外遊びの重要性」を指摘しています。
自然光の下では、目が遠くの景色を見ようとするため、ピントを調整する力が鍛えられます。これが眼の成長や健康を維持する上で重要です。さらに、自然光が網膜に届くとドーパミン分泌され、眼球が伸びすぎて近視になるのを抑えることができます。室内の光より日光の照度が100倍以上とされ、特に午前中の屋外活動が効果的です。これだけ日差しが強いと紫外線の心配もされますが、直射日光でなく日陰や木陰でも効果があります。
外遊びは、子どもの健康維持や基礎体力や運動能力の向上が期待できます。室内での遊びとは異なり、体の複数の部分を連携させて動かす場面も多いため、脳の発達にもつながります。
子どもの積極性を育てるためにも効果的です。家での遊びと比較すると、外遊びは自由度が高いため、子ども自身が積極的に考えて動かなければならない場面も多くあります。子どもは、自然の中でどう遊ぼうか、遊具を使ってどう遊ぼうかなどと考えて自分で動き出すため、積極性が高まります。同じ年代の子どもの遊び方を見て刺激を受けたり、友だちの真似をしたり、一緒に遊ぶことでたくさんの刺激を受けて、自分で積極的に考えて動く力が伸びます。
友だちと外遊びをする場合は、一定のルールに従ったり、会話をしたりしなければなりません。遊具を譲りあうことや、自分の考えを主張することも求められます。さまざまな人と接したり、一緒に遊んだりすることで、みんなで遊ぶ楽しさや協調性の大切さを学ぶことができます。コミュニケーション能力が身につくことはとても大事なことです。
また子どもは、さまざまな失敗経験から多くのことを学んでいきます。危険を避けるためにはどうすればよいか、スポーツがうまくなるためにはどう体を動かせばよいか、友だちと仲よくするためにはどう接すればよいかなど、失敗を糧にしていろいろなことを考え、成長していきます。外遊びは、勉強では身につかない生きる術を学ぶことができるため重要だと考えます。
朝の会の前や中休み・昼休みに校庭で遊んだり、体育の授業や屋外での自然観察や野外事業を増やしていく必要があると考えます。
【質問5】休み時間や体育の事業や屋外での自然観察・野外授業など野外活動の重要性についてどう思われるでしょうか?
【答弁】文部科学省では、将来的な眼疾患のリスクを低減するため「子供の目の健康を守るための啓発資料について」を発出し、視力低下を防ぐための外遊びやスマホの近距離での長時間視聴を続けないこと等を啓発しています。教育委員会でも、屋外活動には、視力の低下を防ぐと共に心身のリフレッシュ、免疫力の強化などの効果があることから、啓発資料を活用し保健だより等を通して、児童生徒や保護者に向けても周知を図っています。
要望
ご答弁ありがとうございました。乳幼児健康検査の受診者総数に対して精密検査対象となった子どもの割合は、屈折検査を導入前3年間の平均と比べて1.7倍であり、早期発見に一定の効果があったものと考えているとのお答えでした。
早期発見により治療することで視力の回復が期待できるので大和市の子どもたちの健康が少しでも良くなることにつながって安堵しています。しかし精密検査を受けていないお子さんの数が一定数いることは確認されています。日々の忙しさでうっかり忘れていることはありがちです。精密検査を受けたか確認が取れなかった方には、一生に関わることですので一人でも多くのお子さんが治療にを受けて視力の回復につながるように、丁寧なフォローを行っていただくよう強く要望致します。
また我が家の子どもは目の検査にひっかからなかったので、6歳までに発見できれば治療により視力が回復するということを知りませんでした。知識として知っていれば自分の子どもがもし、2次検査や精密検査が必要になった時に真剣に取り組みしなければという気持ちになると思います。チラシやホームページで周知をお願い致します。
小中学校の目の健康についてですが、大阪市では「大府市こどもの近視予防プロジェクト」を立ち上げ、こどもの近視予防のための取り組み支援や効果的な啓発に取り組むんでいます。具体的には外遊びの大切さを伝えています。
またスマホ、ゲームや読み書きなどの近業作業時に気を付けることを実践的に学べるよう小学1年生に向けた出前講座を実施しています。。また「親子で目について学ぼう」夏休み体験型イベントで近視の予防や日常生活で気をつけたいことを学んだり、紙粘土で目玉づくりをする工作をしたり、姿勢をただす体幹トレーニングなど楽しく学べるイベント開催しています。子どもたちにやりたいと興味を持ってもらえるような、楽しみながら学べる機会を作っていただけますよう要望致します。
スマホやタブレットを長時間見続けないように20分に20秒など目を休めることを呼びかけしたり、遠くをみる意識づけを学校の中でもしてもらえたらいいなと思います。教室に貼ってある視力検査については、測る場所をテープで貼るなどマーキングし、子どもたちがそこを通るたびにやってみようと思わせるような工夫をしている学校もあると聞いています。そのような取り組みが全学校でも行われるよう校長会などで呼びかけしていただけると効果的だと思います。
屋外で2時間過ごすことで近視のリスクが減ることや家庭でのスクリーン時間の見直しなど、保健だよりやポスターなどで積極的にお知らせして周知に努めていただくよう要望致します。